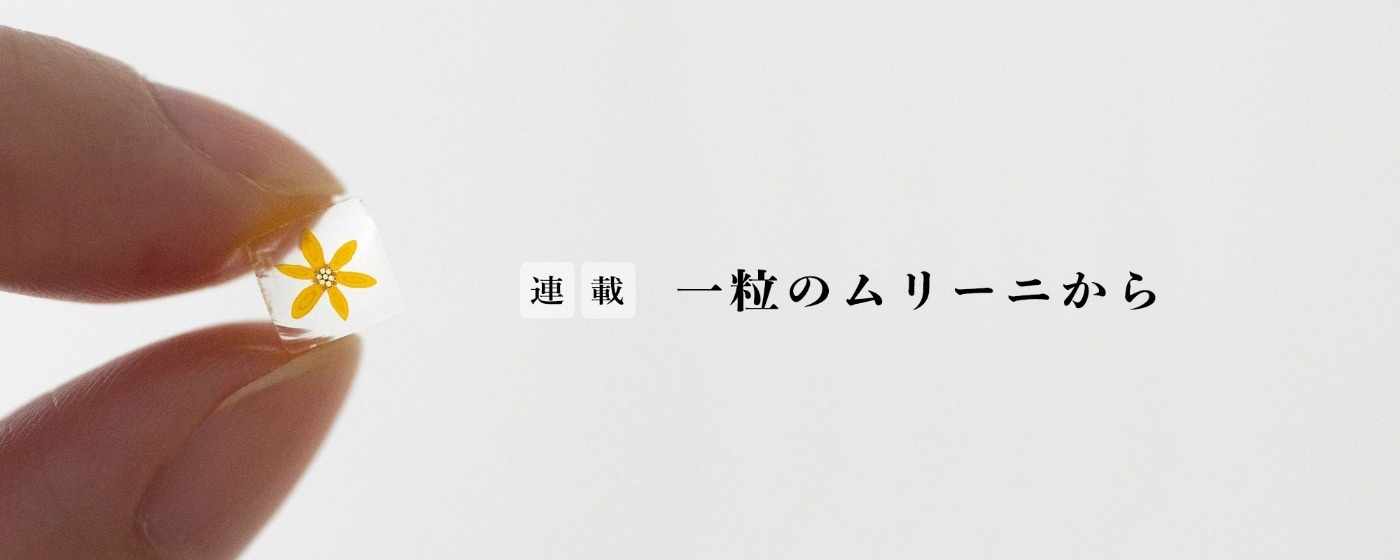
episode 4
「 私のエポックメーキング 」
潮工房でムリーニの制作を始めた当初、私はステンドグラスのように色と色をぶつけ合うような仕事をしたいと考えていました。
というのは、私がアシスタントをしていたアメリカ・ケープコッドのチャダムグラスカンパニーでは、師匠のジム・ホームズさんの仕事は、たとえば紫色のボディに黄色のネックとか、強い色同士を合わせるという吹きガラスだったのです。仕上げ途中の作品をチェックのため光に透かして見ると、まるで教会の中にいるような、ステンドグラスの光に包まれるような気がして心が震えました。色ガラスって何て綺麗なんだろうと…。そんな経験から影響を受けて、私も色と色をぶつけ合うことによって、そういう感覚のものを器の中に閉じ込めたいと思ったのです。
また、私にムリーニのテクニックを教えてくださったリチャード・マーキスさんの仕事は、不透明色のガラスを組み合わせるというムリーニ。ぎっしりと色鮮やかなガラスを使い分けた、そのコンビネーションはとても新鮮でした。
そういうわけで、帰国して潮工房を始めた1998年から2003年くらいまで、私のモザイクガラスは、色同士を組み合わせるという仕事だったのです。
ところが、いろいろとやっていく中で、次の展開が見えてこない、ということが創作においては起こるわけです。私は展覧会を中心にした活動をしているので、展覧会毎にテーマを設けて制作することが多かったのです。これまでの展覧会のいくつかの軌跡から、私のムリーニの転機、展開を振り返ってみます。
2004年の展覧会では、「舟歌」というテーマがありました。少し“揺らぎ”というものを出したいと思ってつけたタイトルです。四角いパーツを組み合わせてつくる技法ゆえに、それまではカチッとしている仕事を良しとしていました。しかし、その頃はカチッとしたパーツを使いながらも、全体の醸し出すものはもう少し揺らぐような感じにしたいなと思って、カヌーの形をした作品をつくりました。模様に、形に、かなり悩んでいた時期でもあり、この頃から一粒一粒の模様を細かくしてみたり、大きい模様と小さい模様を組み合わせてみたりということを始めました。
大きな転機が訪れたのは2005年。ガラス作家・中野幹子さんとの二人展でした。「わ」というテーマの展覧会で、中野さんはもともと鳥獣戯画などを描いていらっしゃって、描くこととガラスを見事に調和させていました。一方で、私は着物の柄や織り、染めから着想した模様を、ムリーニに置き換えて展開してゆきました。とくに着物は太い糸と細い糸を織り交ぜて織ることで性質を中和させて、光沢も見る方向によって変わるよう工夫されているということを本で読み、これはガラスにも使えるかもしれないと思ったのです。いろいろな色を取り混ぜて、規則正しく、あるいは不規則にすることで生まれるリズムを裂地に倣って試み始めました。
このときに最初に思い至ったのが、私の祖父の絞りの帯でした。それをイメージしたときに腑に落ちたというか、ムリーニの仕事が自分のものになってきたかな、という感触を初めて得たのです。独立から7年目のことでした。
その半年後、造り酒屋の福光屋さんが運営するダイニングバー(SAKE鏡花)で開かれた展覧会では、何となくお酒にイメージが近いかなと思って、松と瓢箪柄が組み合わさってリズミカルに並んでいるコップをつくりました。この頃から具象モチーフのムリーニも少しずつつくるようになって、ずいぶんと展開があった時期ですけれど、数量はそれほどつくっていなかったので、私の手元に作品はあまり残っていないのです。いまでも続いている「お酒のきもの」シリーズは、このときに出てきたもので、ムリーニでつくるグラスをお酒がまとう着物に見立て、意匠を考えるようになりました。
そして2008年には、展覧会8回目を記念して「bun bun bun」という蜂のシリーズの展覧会を開きました。小西潮との二人展で、彼のつくるレースの細かいツイスト模様にハニカムと蜂のムリーニを組み合わせ、さらにボトルを8の形でつくったりしました。
2010年には、お花のムリーニに取りかかりました。きっかけはお客様から、60歳の誕生日に「バラだけのムリーニがほしい」というご注文をいただいたことでした。古今東西、ムリーニで花を手がける人はとても多く、いまごろ私が手がけるには大きな課題でしたが…。私は花が好きなので取り組んでみたところ、予想以上に楽しみや悦びがあったのです。それはいまも続いていて、さまざまな種類の花をつくっています。
最初はガラスの色から始まって、それから細かな小紋柄、そして具象が始まりました。具象に取り組んだのは割と遅かったのですけれど、虫や花もあれば、干支、魚、動物、野菜もというふうに、いまではさまざまなところに手を広げています。虫シリーズも蜂、蛍、蜻蛉、蝶、蟻などいろいろですし、野菜シリーズは夏野菜や冬野菜など、おそらく14~15種類はつくってきました。吹き寄せと言って、秋の幾種類もの紅葉した葉っぱを集めたようなものもつくっています。
近年の展開の一つ、2019年の和光ホールさんの展覧会では、「鳥」をテーマにしました。その中には私の一番好きな鳥、白鷺も入っていますし、架空の「虹を描く鳥」という羽根が7色になっている鳥や、少し応用編で「羽根」というものもありました。
また、私のモチーフの一つに、原風景というのがあります。私は埼玉県の田んぼの多いところで育ちましたので、いつも田んぼを見ながら通学していました。田んぼに水が張られて、苗が植わって、青々とした田んぼがひろがって。そこへ風が吹いて、さーっと苗を同じ方向になびかせる様子を見ると、子どもながらに神の存在を感じるような瞬間がありました。あるとき、諏訪湖の御柱祭に行ったときに、そこの友人が御神渡について話をしてくれたのですが、諏訪湖の人は、神の存在というのを湖に感じるんですね。私にとってはそれが田んぼだったのです。たとえば「稲穂と赤とんぼ」のシリーズは、まさにその原体験から来ています。
こうして振り返ると、2005年頃から、私の仕事はずいぶんと変わってきたように思います。そうこうするうちに、リチャード・マーキスさんやヴェネツィアで行われているムリーニとは違う道を歩んでいて…。それは、私が日本人だからだと思います。ビジュアル的に家に飾るものよりは、器にしたい、手に取って愛でるものをつくりたい、というところが大きかったと思います。
器にするには、それなりの軽さとか、バランスというものが必要になりますし、透かしたときにどう面白いかとか、飲んだときにどう見えるか感じるか、ということを考えます。掌におさまったときにどの位置にどの模様が来たらいいのか、どういう色が来たらいいか、どのくらいの薄さかというのが決まってきます。そこを追っているうちに、またはどう季節を取り入れたらいいのかということを考えるうちに、少しずつ変わってきたのだなと思います。
欧米の器の中にも、器を愛でるというのはあるのですけれど、飾るという文化の方が主流のように感じます。小さな物であっても、それを飾って置くということが富の象徴であったりするので、やはり基本は自分の手の中で愛でるというよりは、飾ってインテリアとして楽しまれています。そうしたところに、私の作品と他の国、他の作家との作品の違いが出てきたのかもしれません。
episode 1ムリーニの起源・語源
episode 2ムリーニとの出会い、変遷 ~前編 ~
episode 3ムリーニとの出会い、変遷 ~後編 ~
episode 4私のエポックメーキング~











